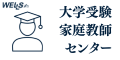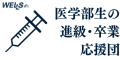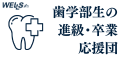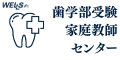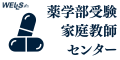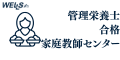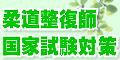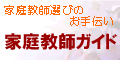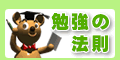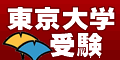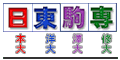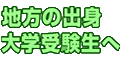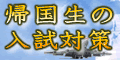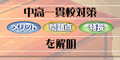薬学部の志望校選びの進め方

薬学部を目指す受験生にとって、志望校選びは大きな悩みの種です。大学や学部の選択肢が多く、どこを志望校にすれば良いのか親子で迷ってしまうことも珍しくありません。保護者としてはお子さんの将来を思い、できるだけ確実で安心な進路をと考える一方で、お子さん自身は「この大学で学びたい」「この分野に興味がある」といった情熱や憧れを重視しがちです。まずは親と子で視点に違いがあることを理解し、一緒にベストな志望校を見つけるステップを踏んでいきましょう。
親と子の視点の違いを理解する
志望校を選ぶ際、親と子では重視するポイントが異なることがあります。例えば子どもは学びたい学部の有無や大学の雰囲気、ネームバリューなどに目が行きがちですが、親は学費や自宅からの距離、卒業後の就職状況など現実的な条件が気になるものです。こうした視点の違いがあるのは自然なことです。「親の期待と子どもの希望にギャップがあるのでは」と不安になる必要はありません。大切なのは互いの考えを知り、尊重し合うことです。まずはお子さんの希望(学びたい分野、憧れの大学、将来の目標など)をしっかり聞きましょう。その上で保護者の考える条件(学費負担、通学の安全性、将来の安定など)も素直に伝えます。双方が何を大切にしているか理解することで、冷静に候補を絞り込む土台ができます。
情報収集は親が積極的にサポート
志望校選びには豊富な情報が欠かせません。現役の受験生であるお子さんは日々の勉強に忙しく、大学調べに手が回らないこともあります。そこで情報収集は保護者がサポートしましょう。具体的には、各大学の薬学部の特色や教育内容、6年制と4年制の違い、取得できる資格(薬剤師国家試験の受験資格など)を調べて整理します。薬学部には6年制課程(薬剤師養成)と4年制課程(主に研究者養成)があるため、お子さんの将来像に合った課程を提供している大学かどうかを確認することも重要です。また、大学の公式サイトやパンフレットで入試科目や難易度(偏差値)、卒業生の進路(製薬企業への就職状況や病院薬剤師になる割合など)もチェックしましょう。夏休みなどに開催されるオープンキャンパスや説明会には、ぜひ親子で参加することをおすすめします。キャンパスの雰囲気や設備、在学生の様子を肌で感じられるほか、教授や在学生から直接話を聞くことで、志望校のイメージが具体的になるでしょう。保護者自身も大学スタッフに質問し、不明点を解消できます。こうした情報収集を重ねることで、各大学の魅力や課題が見えてきて、お子さんも自分に合った志望校像をつかみやすくなります。
模試結果や学力から現実的な候補を検討する
志望校を考える際には、現在の学力や模試の判定も参考にしましょう。お子さんの成績が志望校の合格ラインにどの程度届いているかは、現実的な目安になります。ただし、模試の判定が思わしくないからといって、最初から夢を諦めさせる必要はありません。大切なのは現状を踏まえて対策を立てることです。お子さんと一緒に模試結果を見ながら、強みと弱点を分析しましょう。例えば、化学や数学で高得点が取れているなら、その調子を維持できる大学を安心材料にできますし、英語が苦手なら入試で英語の配点が高すぎない大学も検討するといった具合です。また、「第一志望」「滑り止め(安全校)」「チャレンジ校」といったランク分けも有効です。第一志望はお子さんの夢を優先して多少高い目標でも設定し、安全校は確実に合格圏内の学校を1〜2校用意します。そしてチャレンジ校として実力相応かやや上位の大学も視野に入れておくと、万一のときの進路にも幅が生まれます。こうした候補校の検討は、親の方が客観的に助言しやすい部分です。ただし最終的にはお子さん自身が納得できる選択肢を残すようにしましょう。「これくらいが現実的だからここにしなさい」と一方的に押し付けては、子どももやる気を失ってしまいます。あくまでも現実的な視点を提供する役割に徹し、決定権は本人にゆだねる姿勢が大切です。
子どもの意思を尊重し最終決定を後押し
情報が出揃い、いくつか候補が絞れてきたら、最後はお子さんの意思を尊重して志望校を決定しましょう。保護者としては「あの大学の方が就職によさそうでは?」など気になる点もあるかもしれません。しかし、お子さん自身が「ここで学びたい」という強い思いを持てる大学こそ、合格に向けて最大限の努力を引き出せる志望校です。子どもが悩んでいる場合は、焦らず背中を押してあげましょう。「あなたが本気で目指したいと思える大学なら、親として精一杯応援するよ」と伝えることで、お子さんは安心して自分の気持ちに正直になれます。いったん志望校が決まれば、受験勉強のモチベーションも飛躍的に高まります。「絶対に○○大学の薬学部に合格するんだ」という目標が明確になれば、辛い勉強も乗り越える力になります。また、志望校が決まった後も親子の対話は続けましょう。時折「最近○○大学でこんな研究が盛んらしいね」「キャンパス周辺の住環境はどうかな?」といった話題を振り、お子さんの気持ちを盛り上げるのも効果的です。最終決定した志望校は親子の二人三脚で目指すという意識を共有し、合格へ向けて前向きに歩んでいきましょう。
志望校選びは、受験勉強のスタート地点とも言えます。親子でじっくり話し合い、情報を集め、現実と夢のバランスをとりながら決めた志望校であれば、お子さんも納得して受験勉強に打ち込めるはずです。保護者にとっても心配は尽きないものですが、最後はお子さんの意思を信じてあげてください。「この大学に行きたい」というお子さんの想いを尊重しつつ、親としてしっかり支える——その姿勢があれば、きっと志望校選びもうまくいくでしょう。以上のステップを踏んで、後悔のない志望校選びを親子で実現してください。