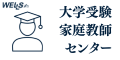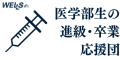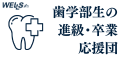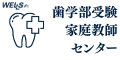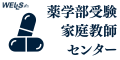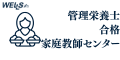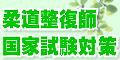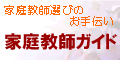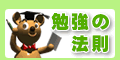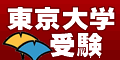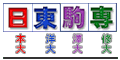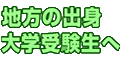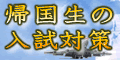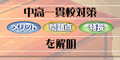薬学部受験で失敗しない学習計画の立て方
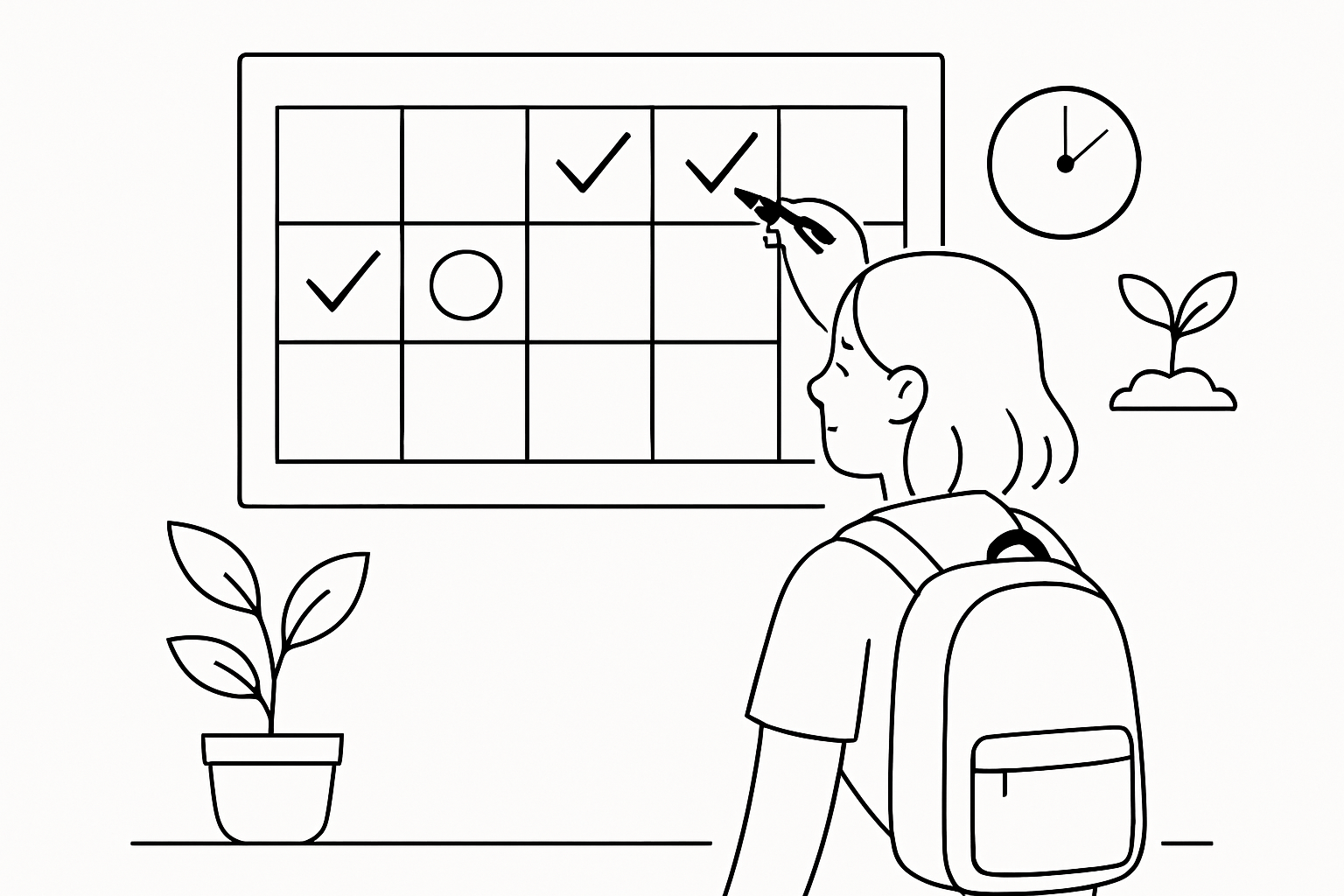
薬学部合格という目標に向けてお子さんが日々勉強に励む中、計画的な学習は合格への近道です。闇雲に勉強するのではなく、しっかりと計画を立てて進めることで効率が上がり、モチベーションの維持にもつながります。しかし、計画倒れになってしまう受験生も少なくありません。ここでは失敗しない学習計画の立て方を紹介し、保護者としてお子さんをどのようにサポートできるかを考えてみましょう。
合格から逆算して全体計画を立てる
まずは入試本番までの全体像を把握することが大切です。志望校の入試日程や共通テストの日程を確認し、「あと何ヶ月で試験」というゴールから逆算して計画を立てましょう。例えば残り1年であれば、年間計画として「夏までに基礎固めを完了する」「秋から過去問演習を始める」など大まかな目標を設定します。年間計画があると、今どの段階にいるかがお子さん自身にも明確になり、見通しを持って勉強に取り組めます。次に、それをベースに月間・週間計画へと落とし込みます。月ごとに「英単語帳を○月までに○周する」「○月の模試で偏差値〇〇を目指す」といった目標を定め、週ごと・日ごとのタスクに分解します。最初に大枠のゴールを決め、その後細かなステップに分ける逆算思考で計画を組むと、日々の勉強がゴールに直結していることを実感でき、やる気も高まるでしょう。
無理のないスケジュール設定
計画を立てる際、意欲が高まるあまり詰め込みすぎたスケジュールを立ててしまうのは失敗の元です。最初から1日10時間勉強など過度に高いハードルを設定すると、達成できずに挫折感を味わってしまいがちです。ポイントは「確実に実行できる量」からスタートすること。例えば、平日は部活や学校行事もあるなら「平日は毎日3時間、土日は5時間勉強する」といったように、現実的にこなせる範囲で計画します。慣れてきたら徐々に勉強時間を増やしたり難易度を上げたりすれば十分です。また、休息時間や自由時間も計画に組み込むことを忘れないでください。長時間休みなく詰め込むと集中力が続かず、結局効率が落ちてしまいます。毎日適度に休憩や気分転換の時間を設ける方が、心身の健康を保ちながら継続的に勉強できます。さらに計画には予備日を作りましょう。体調不良や急な用事で計画通りに進まない日もあるはずです。予備日があれば遅れを取り戻せるので、計画が崩れにくくなります。お子さんには「計画通りにいかなくても大丈夫。リカバリーできるようにしてあるからね」と声をかけ、プレッシャーを和らげてあげることも大切です。堅実で柔軟性のある計画こそ、長続きする計画です。
弱点強化と得意科目のバランス
薬学部受験では英語、数学、化学、生物(または物理)など複数科目の勉強が必要になります。学習計画を立てる際には、お子さんの得意科目と苦手科目のバランスにも配慮しましょう。苦手科目ばかりに時間を割きすぎると得意科目の力が錆び付いてしまいますし、逆に得意科目だけをやって安心していては苦手を克服できません。例えば、化学が苦手で英語が得意なお子さんの場合、平日の計画には化学の基礎問題演習を毎日少しずつ入れ、英語は長文読解を隔日で行うなどバランスを取ります。1週間単位で見たときに全ての科目に触れている状態が望ましいです。特に薬学部は化学や生物が合否を左右しやすいので、苦手意識があるなら早めに集中的に強化する期間を計画に盛り込みましょう。その際、基礎固めから始め、無理なくレベルアップする段階的な計画にすると挫折しにくくなります。得意科目については、演習量を確保して更なる得点源に伸ばす計画を立てつつ、時折弱点補強とのメリハリをつけると良いでしょう。親御さんは、お子さんの模試の成績表などを一緒に見ながら、「この科目は順調だね」「ここはもう少し頑張ろうか」と声をかけ、計画配分の調整に協力してあげてください。
定期的な見直しと軌道修正
完璧な計画を立てても、常にその通りに進むとは限りません。むしろ計画は途中で見直す前提でいる方が成功しやすいのです。月末や模試の後など、節目ごとに計画の進捗を親子で確認しましょう。「この1ヶ月で予定の参考書が終わらなかった」「思ったよりも数学に時間がかかっている」などのズレが生じていれば、次の月の計画で調整します。計画通りにいかないことを悲観する必要はありません。うまくいかなかった部分はなぜ遅れたのか原因を分析し、計画の方を現状に合わせて修正すれば良いのです。例えば、予想以上に時間がかかった科目は1日の配分を増やす、逆に順調な科目は少し配分を減らす、といった微調整をします。このようにPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)のように計画と実行を回していくことで、計画倒れを防ぎやすくなります。保護者の方は、定期的なミーティングのような形でお子さんと計画を振り返る機会を作ってあげましょう。頑張りを労いながら、「ここは予定以上に進んだね、すごい!」「ここは予定より遅れたけど、じゃあ来月取り戻そう」と前向きに声をかけることで、お子さんもモチベーションを維持できます。
保護者ができるサポート
学習計画を立てるのも実行するのも基本的にはお子さん本人ですが、保護者のサポートがあると計画の効果は倍増します。まず、計画立案の段階では一緒にスケジュールを書き出してみると良いでしょう。市販の学習計画表やカレンダーに予定を書き込んだり、ホワイトボードに今週の勉強メニューを書いて見える化したりすると、親も進捗を把握しやすくなります。お子さんが計画通りに勉強を進めていたら小さな達成を認めて褒めることも大切です。「予定の教材が終わったんだね、頑張ったね!」と声をかけると、お子さんは次も計画を守ろうという気持ちになります。逆に計画通りにいかない日があっても、頭ごなしに叱責しないようにしましょう。「今日は疲れていたのね。じゃあ明日の計画で調整しようか」と寄り添えば、お子さんも安心してリカバリーできます。また、必要に応じて家庭教師や塾などプロの力を借りることも検討してください。第三者のアドバイスが入ることで計画に対する緊張感が生まれ、お子さんの意識も高まります。最後に、家庭内で勉強に集中できる環境を整えるのも重要なサポートです。計画した時間に集中できるよう、静かな学習スペースの確保やスマホ利用のルール作りなど、環境面の工夫もしてみてください。
学習計画は立てることがゴールではなく、実行してこそ意味があります。計画に沿って学習が進めば自信につながり、さらに勉強がはかどる好循環も生まれるでしょう。うまくいかない時も柔軟に立て直せば大丈夫です。保護者のサポートのもと、上手に計画を活用して薬学部合格への道を歩んでください。