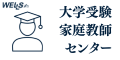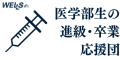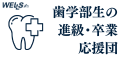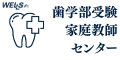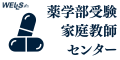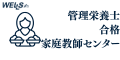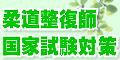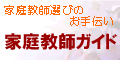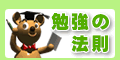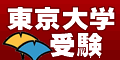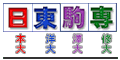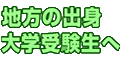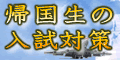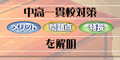薬学部入試の面接・小論文対策で差がつくサポートとは
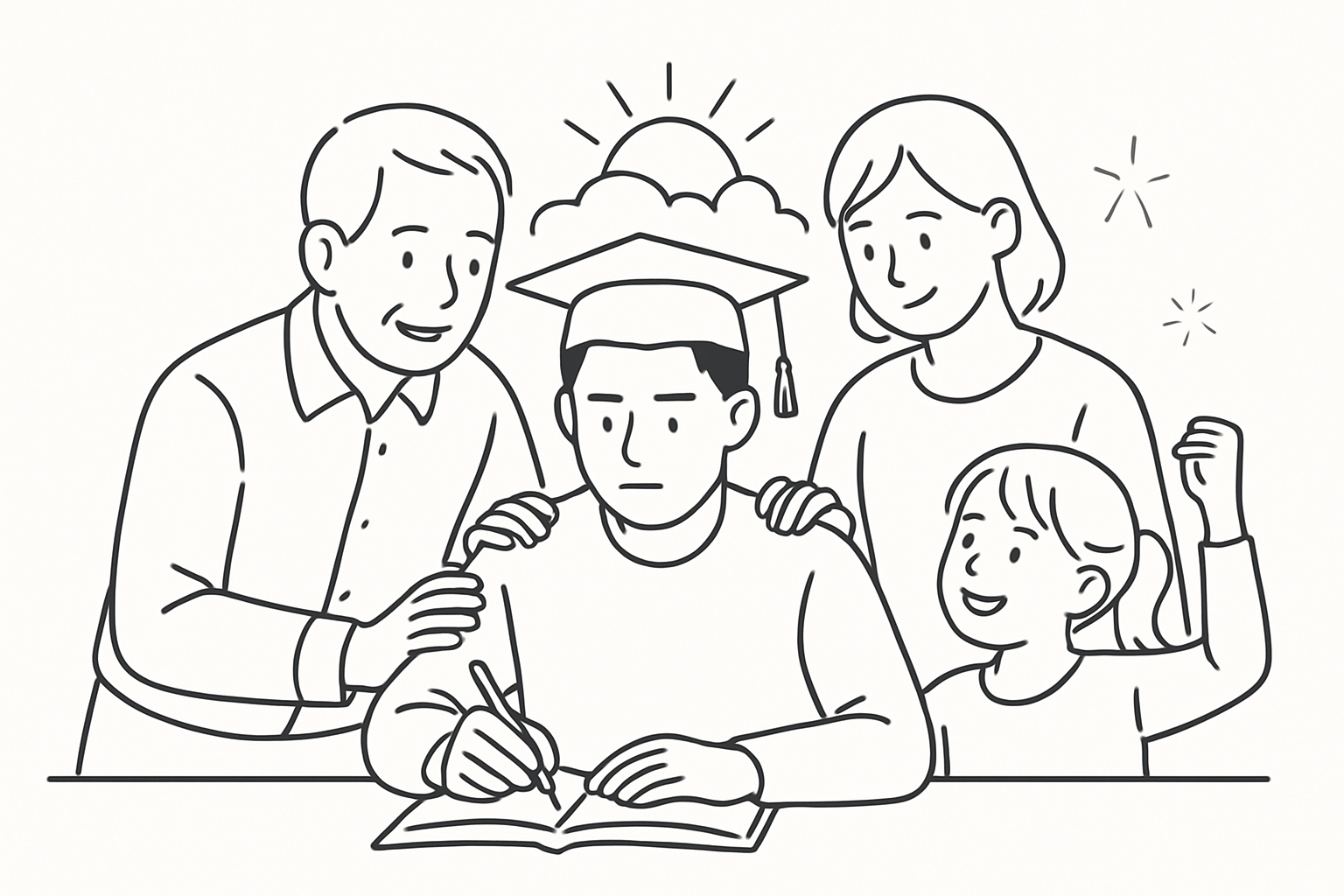
大学入試において、筆記試験の点数だけでなく面接や小論文が合否の鍵を握るケースがあります。特に薬学部では、推薦入試や総合型選抜で面接・小論文が課されることも多く、人柄や思考力が評価の対象となります。こうした対策は学力とは別軸の準備が必要なため、周囲の受験生と差がつきやすいポイントです。保護者として、お子さんの面接・小論文対策にどのように関与できるかを考えてみましょう。
志望理由の明確化をサポートする
まず、お子さんが「なぜ薬学部に進みたいのか」を自分の言葉で語れるようサポートしましょう。面接でも小論文でも必ず問われるのが志望動機です。薬剤師になりたい理由、薬学に興味を持ったきっかけ、将来どんな貢献をしたいか――これらを明確にしておくことで回答に一貫性と熱意が生まれます。保護者としては、日常会話の中で「どうして薬に関わる仕事がしたいと思ったの?」「将来はどんな薬剤師になりたいの?」といった問いかけをしてみてください。お子さんが自分の考えを話すのをじっくり聞き、肯定的に受け止めることで、考えを整理する手助けになります。また、お子さん自身が気付いていない長所やエピソードを家族だからこそ知っている場合もあります。「小さい頃からコツコツ理科の実験をするのが好きだったよね」「困っている人を見ると放っておけない優しいところがあなたの良さだよ」など、保護者目線で感じるお子さんの魅力を伝えてあげましょう。本人が当たり前と思っている経験や強みが、志望理由を語る上で大切なアピールポイントになることがあります。そうしたヒントを与えることで、お子さんは自分の志望理由をより具体的で説得力のあるものに練り上げていけるでしょう。
模擬面接で練習の機会を作る
面接対策で効果的なのは、模擬面接の練習です。家庭でも簡単に模擬面接の場を作ることができます。保護者が面接官役となり、お子さんに自己紹介や志望動機、学生時代に力を入れたことなどを質問してみましょう。最初は少し照れ臭いかもしれませんが、回数を重ねるうちにお子さんも真剣に答えられるようになります。ポイントは、本番さながらの形式で行うことです。リビングではなく机に向かい合って座る、ノックの仕方や椅子への腰掛け方から始めるなど、細部にもこだわってみましょう。質問内容も、薬学部ならではのものを取り入れてみます。「将来どのような薬剤師になりたいですか?」「なぜ本学の薬学部を選んだのですか?」といった定番に加え、時事問題や医療に関する自分の意見を問う質問が出る場合もあります。例えば医療の時事問題などを題材に質問される可能性もあります。難しく感じますが、普段から親子で医療・科学の話題に触れておけば落ち着いて答えられるでしょう。模擬面接の練習後には、良かった点と改善点をフィードバックしましょう。「笑顔でハキハキ答えられていて良かったよ」「内容はまとまっていたけど、もう少し結論を先に言えるとわかりやすいかな」など、具体的に伝えます。自分では気付かない癖(小さい声になってしまう、視線が泳ぐ等)も家族なら指摘しやすいです。こうした練習を積むことで、本番の面接でも落ち着いて受け答えができ、他の受験生との差につながります。
小論文の知識を広げる手助け
小論文対策では、書く練習と同じくらい知識のインプットも重要です。薬学部の小論文テーマは、医療や科学技術、生命倫理、社会問題など多岐にわたります。お子さん一人でこうした幅広い話題に精通するのは大変ですから、保護者も一緒に知識を広げるサポートをしましょう。例えば、新聞やニュースで医療・薬事の話題を見かけたら親子で意見交換してみましょう。新薬の開発や高齢化による医療費などについて話し、お子さんの考えを否定せず「なるほど」と受け止めつつ、「もし薬剤師ならどうする?」と問いかけてみるのです。また、小論文のテーマによく出るキーワード(例えば「チーム医療」「創薬」「セルフメディケーション」など)について一緒に調べ、基本的な知識を整理しておくのも有効です。家庭にある図鑑やインターネットを活用し、ミニ勉強会のような形で楽しく知識を蓄えると良いでしょう。知識が増えれば書ける内容も豊かになり、自信を持って小論文に臨めます。
書いた小論文への客観的アドバイス
お子さんが練習で書いた小論文の読者になってあげることも、大きなサポートになります。仕上がった小論文を保護者が読んでみて、素直な感想や気付いた点を伝えましょう。「とても読みやすかったよ」「この部分の主張が少し伝わりにくかったかな」など、専門家の添削ほど高度でなくて構いません。大切なのは、客観的な視点を提供することです。お子さん自身は一生懸命書いているので、自分の文章の欠点になかなか気づけないものです。そこで保護者が一般読者の目線で「結論は何かもう一度確認してみようか」「段落の繋がりが少し飛んでいるかも」などと助言すると、お子さんは自分の小論文を見直すきっかけが得られます。必要に応じて学校の先生や家庭教師にも小論文を読んでもらい、意見を聞いてみるのも良いでしょう。第三者のアドバイスを取り入れつつ、本人が納得できる形に練り直すプロセスを繰り返すことで、小論文の完成度は格段に上がります。保護者としては、あくまで励まし役に徹し、細かな表現のミスを責めたりせず「着実に良い文章になってきているね」と成長を認めてあげることがポイントです。
自信と本番力を引き出す親のかかわり
面接や小論文で実力を発揮するには、お子さんが自信を持って本番に臨めることが何より大切です。保護者ができる最後のサポートは、お子さんの緊張を和らげ、本来の力を出し切れるようメンタル面で支えることです。例えば面接当日の朝、「大丈夫、あなたならきっと伝わるよ」と笑顔で送り出してあげましょう。小論文試験の日には「落ち着いてね。いつも通り書けば大丈夫」と声をかけます。これまで一緒に準備してきたという事実が、お子さんの心の支えになります。たとえ本番で予想外の質問が来ても、日頃から親子で議論していれば柔軟に答えられるはず、といった安心感が生まれるのです。また、試験が終わった後は労いと肯定の言葉をかけてください。「よく頑張ったね。きっと思いは伝わったよ」と結果に関係なくねぎらうことで、お子さんもやり切った達成感を持てます。他の受験生が学科試験の勉強に追われて面接・小論文対策がおろそかになる中、親子でしっかり準備してきた経験は大きな財産です。保護者のサポートが生む自信こそが差をつける決め手になり得ます。
面接・小論文対策は、親が関われる貴重な領域です。お子さん一人では準備が難しい部分だからこそ、寄り添ったサポートが光ります。親子で試行錯誤しながら練習を積めば、お子さんは表現する力と思考力を飛躍的に伸ばすことができるでしょう。そして何より、「自分はこんなに準備してきた」という自信が本番での堂々とした振る舞いにつながります。保護者の温かな後押しで、お子さんが面接・小論文でも力を発揮し、薬学部合格への大きなアドバンテージを得られるよう願っています。