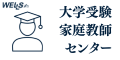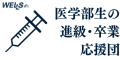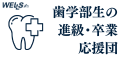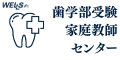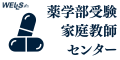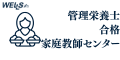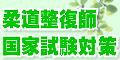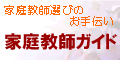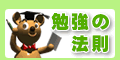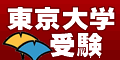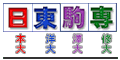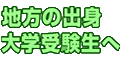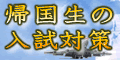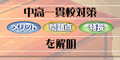薬学部志望の浪人生のメンタルと親の接し方
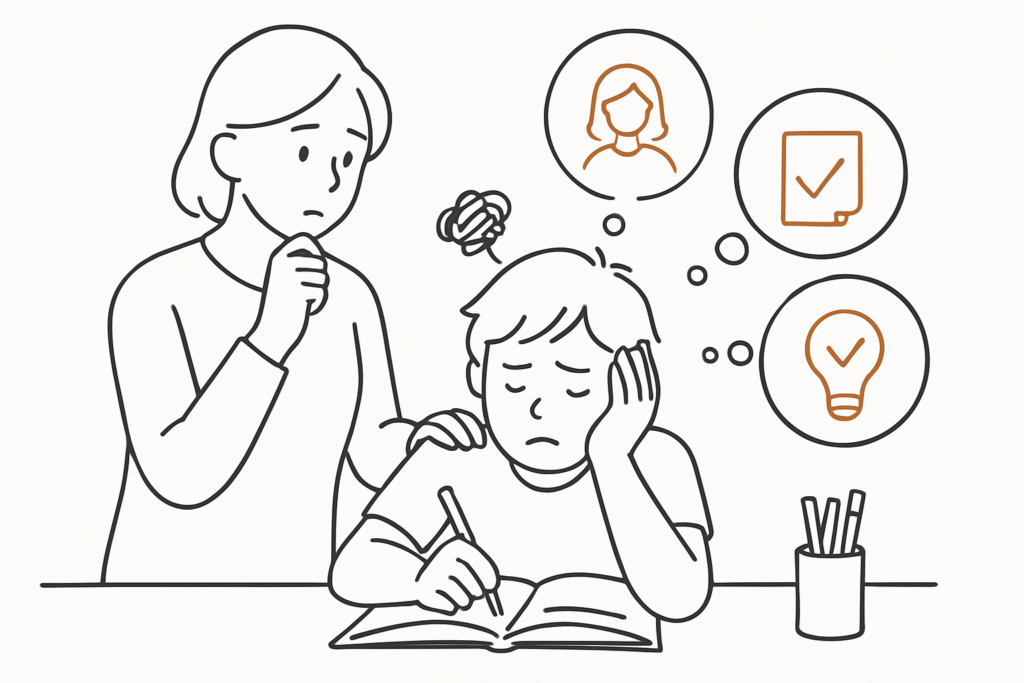
第一志望の薬学部合格をめざし浪人生活を送るお子さんを支えるには、メンタル面でのサポートが欠かせません。現役合格を逃し、周囲の同級生が大学生活を始める中で勉強を続けることは、お子さんにとって大きなプレッシャーと孤独感を伴うものです。保護者として、どのように声をかけ、どのような距離感で接するのが良いのでしょうか。浪人生の心情を理解し、前向きにサポートする接し方のポイントを考えてみます。
浪人生が抱えがちな不安と孤独を理解する
まず、浪人生のお子さんが置かれた状況を理解しましょう。高校を卒業した同級生の多くが大学へ進学していく中、自分だけがもう一年受験勉強を続けることになった――この事実だけでも、お子さんは取り残されたような不安を感じやすいものです。「来年も落ちたらどうしよう」「周りは先に進んでいるのに自分は…」といった焦りやプレッシャーが心を重くします。また、現役時代とは異なり浪人生にはクラスメイトのような仲間が身近にいません。予備校や塾に通っていても、周囲は見知らぬ人ばかりで、気軽に悩みを共有できる友達がいないケースも多いでしょう。文化祭や体育祭といったイベントもなく、毎日が勉強の繰り返しになりがちな浪人生活では、知らず知らずのうちに孤独感が募ります。こうした不安と孤独が、浪人生のメンタルに影を落としがちです。保護者の方には、まずお子さんがそうした複雑な思いを抱えている可能性に思いを巡らせていただきたいです。勉強に集中して頑張っているように見えても、心の中では様々な葛藤があることを念頭に置いて接することが大切です。
「いつも通り」の接し方と過度な干渉を避ける
浪人生の子どもに対して、親御さんはどう接するのが良いのでしょうか。大前提として意識したいのは、現役時代と同じように「いつも通り」接することです。浪人したからといって特別扱いしすぎたり、逆に腫れ物に触るように距離を置いたりすると、お子さんは戸惑ってしまいます。具体的には、朝夕の挨拶や食事の団欒など家族としてのコミュニケーションはこれまで通り続けましょう。勉強の話題ばかりにならないよう、時には趣味の話や時事ネタで雑談するのも良い気分転換になります。一方で、干渉しすぎないことも重要です。「今日は何時間勉強したの?」「ちゃんとやってるの?」と頻繁に聞かれれば、お子さんはプレッシャーを感じるばかりか、「信用されていないのでは」と萎縮してしまうかもしれません。お子さんが自分から勉強の話題を出さない時は、親の方から無理に踏み込まず見守る姿勢も必要です。日々声をかける際も、「頑張りなさい」ではなく「体調は大丈夫?」「何か手伝えることある?」といったサポートする姿勢を示す言葉がけを心がけましょう。普段通りの穏やかな家庭環境を維持しつつ、お子さんの自主性を尊重した距離感を保つことが、浪人生活を支える基本スタンスです。
ネガティブな言葉を前向きに言い換える
長い浪人生活では、お子さんがふと弱音を吐く場面もあるかもしれません。「今年も落ちたらどうしよう…」「自分には無理かもしれない…」そんなネガティブな言葉を聞いたときこそ、保護者の出番です。お子さんの不安に寄り添いつつ、それを前向きな言葉にリフレーミング(言い換え)して返してみましょう。例えば「今年も落ちたらどうしよう」という嘆きには、「不安になるのは一生懸命頑張っている証拠だよ。努力はきっと結果につながるから大丈夫」と励まします。「苦手科目ばかりでダメだ」というような発言には、「向上しているからこそ、苦手がはっきり見えてくるもの。一つひとつ対策していけば大丈夫」と肯定的に返すとよいでしょう。このように、悲観的な見方を希望の持てるメッセージに置き換えて伝えることで、お子さんの落ち込んだ気持ちをそっと持ち上げる効果があります。重要なのは、決してお子さんの弱音を否定したり叱ったりしないことです。「そんな弱気でどうする!」などと叱咤してしまうと、かえって心を閉ざしてしまうかもしれません。むしろ「そう思う時もあるよね」と一度受け止めつつ、最後に明るい展望を示す言葉を添えるのがポイントです。親御さんのポジティブな言葉は、お子さんにとって心の支えとなり、また頑張ろうという気持ちを呼び起こしてくれるでしょう。
努力を認め自信を育てる
浪人中のお子さんは、結果が出ない期間が続くことで自信を失いがちです。だからこそ、日々の努力を認めてあげることが大切です。模試の判定や成績が芳しくなくても、「毎日ちゃんと勉強を続けていて偉いね」「前回よりここが良くなっているね」と、努力や進歩している点を具体的に褒めましょう。親からの承認は、お子さんの自己肯定感を高め、「自分はやれる」という自信につながります。特に薬学部の受験勉強は科目も多くハードです。親御さんにとっては当たり前に映るかもしれない日々の勉強も、実は大変な頑張りの積み重ねです。そのことを忘れずに、「頑張っている姿をちゃんと見ているよ」と伝えてあげてください。また、時には気分転換の提案もしてみましょう。長時間の勉強が続くと精神的に疲弊します。本人は「休んではいけない」と思い詰めているかもしれませんが、親から「少し休憩しようか。散歩でも行く?」と声をかけてもらえれば、安心して気分転換できます。適度にリフレッシュすることで、結果的に勉強の効率も上がり、自信回復にもつながるでしょう。お子さんの努力を認め、小さな成長を一緒に喜ぶ姿勢が、メンタル面の支えとなり、粘り強く挑戦を続ける力を育むのです。
安心できる家庭の雰囲気作り
最後に、家庭内の雰囲気にも目を向けましょう。浪人生にとって家庭は勉強と生活の拠点です。そこが安心できる場所であることは、メンタルの安定に直結します。親御さん同士や家族内で受験のことで口論になったり、重苦しい空気が漂ったりしないように気を配りましょう。保護者自身も不安や焦りを抱えているかもしれませんが、それをなるべく表に出さず、おおらかな態度で日々を過ごすことを心がけてください。例えば、成績の話題で家庭内がピリピリしそうなときは、あえて別の明るい話題に切り替えるなど、雰囲気作りに配慮します。また、受験勉強はあくまでお子さん自身の挑戦であることを尊重し、結果がどうであれ受け止めるという姿勢を示すことも、家庭の安心感につながります。「あなたが納得いくまで頑張るのを応援するし、もし思うような結果が出なくても私たちはあなたの味方だよ」というメッセージを、折に触れて伝えてあげてください。家族に見守られているという安心感が、お子さんのメンタルを支える大黒柱になります。
浪人生のメンタルケアは決して特別なことではなく、親子の信頼関係と温かな日常生活の積み重ねがそのまま支えになります。お子さんにとって、親が変わらず自分を信じて寄り添ってくれることほど心強いものはありません。薬学部合格という目標に向かう長い道のりの中で、保護者の適切な接し方がきっとお子さんの力となるでしょう。家庭が安らぎと勇気を与える場であり続けるよう、ぜひ見守り支えてあげてください。