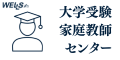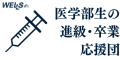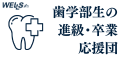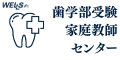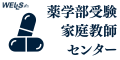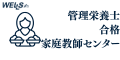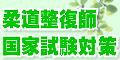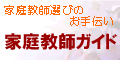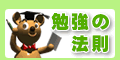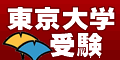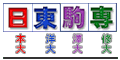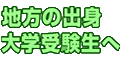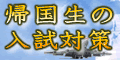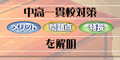【薬学部 勉強 つまらない】 勉強が苦痛だった僕が『面白い』と言えるまで――効率重視で変えた日々
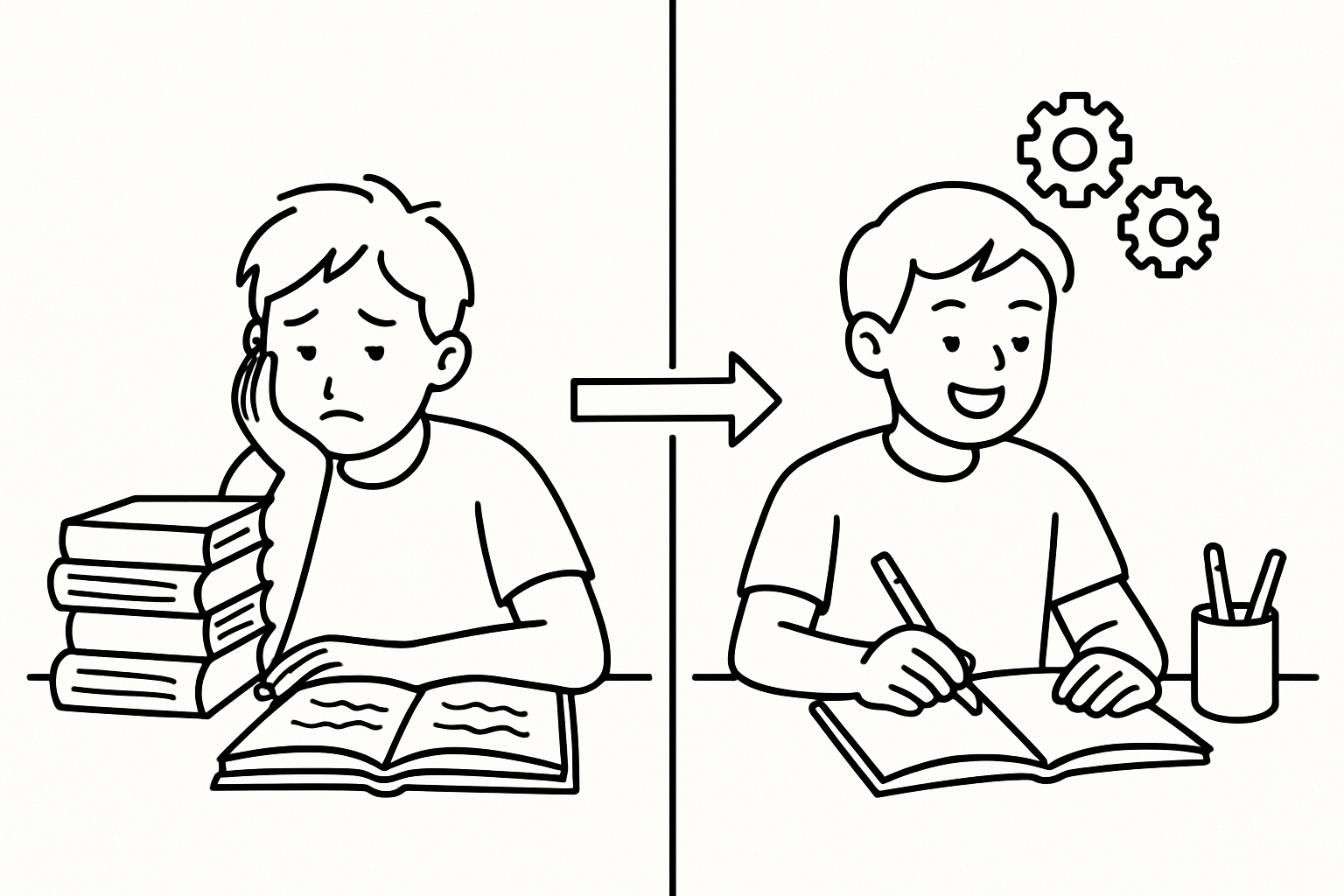
予備校時代、僕は「授業を受ける=勉強した」と思い込み、ノートだけが増えて成績は止まったまま。努力が空回りする無力感に押しつぶされそうでした。ウェルズの家庭教師に切り替えた初日、先生が言ったのは「知識は倉庫じゃない。流通させて初めて価値になる」という一言です。
提示されたルールはインプット三、アウトプット七。参考書は各科目二冊までに絞り、一周を一週間で回す高速サイクル。章が終わるたびに「解説を口頭で再現」するテストがあり、説明があいまいだとホワイトボードで再現を求められます。恥ずかしさもありましたが、“曖昧ゾーン”が瞬時に浮き彫りになるので補強も最速。
秋から導入した“達成度グラフ”では、毎晩セルに理解度を入力。先生がGoogleスプレッドシートで自動生成する右肩上がりの折れ線グラフを見るたび、ゲームのスコアが伸びるような快感を覚えました。
さらに週一回の「ミニ研究発表」では気になる薬品を選び、構造・作用機序・臨床利用をプレゼン。その準備過程で知識が線としてつながり、初見問題にも強くなりました。
十一月の全国模試で偏差値六十から六十八へジャンプ。先生が送ってくれた言葉は「効率は才能に勝る」。試験本番でも解説の実況中継を頭で行い、時間を余して解答を見直せました。番号を見つけた瞬間、思い浮かんだのはあのグラフです。もし「勉強が苦痛」と感じるあなたがいるなら、効率の魔法をぜひ体験してみてください。